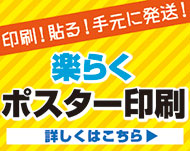【シンポジウム1】 GSA-GSJ Joint Symposium
テーマ『Evolutionary Genetics in the Genomic Era: Understanding Biological Diversity』
1日目(9/6)9:00〜12:00 A会場(パレアホール)
Organizers: Junko Kanoh (University of Tokyo), Naoki Irie (University of Tokyo), Yasunori Aizawa (Tokyo Tech), Masato Nikaido (Tokyo Tech)
- テーマの概要とねらい
- This symposium is an annual international symposium jointly organized by the Genetics Society of Japan (GSJ) and Australasia (GSA). This symposium will focus on evolution and genetics, with six speakers (two from the Australasian side) discussing the mechanisms for generating biodiversity, which have become increasingly well understood through genome-wide analysis. Although the target organisms are diverse, ranging from nematodes to mammals, they are all firmly connected by the principle of genetics.
- プログラム
- S1-1 Lee Ann Rollins (University of New South Wales)
Title: Molecular mechanisms underlying rapid evolution during invasion - S1-2 Takahiro Yonezawa (Hiroshima University)
Title: Population genomic analysis unveils the origins and histories of Japanese native chickens - S1-3 Yohey Terai (The Graduate University for Advanced Studies: SOKENDAI)
Title: The origin and evolution of the dog - S1-4 Frank Grutzner (University of Adelaide)
Title: Mammalian Sex Chromosome Evolution: Lessons from the Egg-Laying Platypus and Echidna - S1-5 Takashi Hayakawa (Hokkaido University)
Title: Genomic convergence of the arboreal species in primates and marsupials - S1-6 Kohta Yoshida (National Institute of Genetics)
Title: Genome-structural evolution driving speciation in Pristionchus nematodes
【シンポジウム2】 共催:新学術領域 非ゲノム情報複製
テーマ『非ゲノム情報複製機構による生命現象の制御』
1日目(9/6)14:00〜17:00 A会場(パレアホール)
世話人: 石黒 啓一郎(熊本大学)
- テーマの概要とねらい
- 非ゲノム情報はゲノム情報と同様に一定の堅牢性を賦与された遺伝情報として働き正確に複製されるとともに、発生シグナルや外的ストレスなどにより変化する可塑性も併せ持つ。本シンポジウムでは有性生殖に関わる発生分化や性決定など生命現象の制御における非ゲノム情報の複製機構についてのテーマを中心に講演を行う。
- プログラム
- S2-1 石黒 啓一郎(熊本大学 発生医学研究所)
「減数分裂開始機構の雌雄性差」 - S2-2 井上梓(理化学研究所)
「経世代ヒストン修飾の確立機構」 - S2-3 立花誠(大阪大学 生命機能研究科)
「マウス性決定のエピジェネティック制御機構」 - S2-4 田中実(名古屋大学 理学研究科)
「卵形成コミットの分子機構から見えてくる卵の特徴」 - S2-5 齋藤都暁(国立遺伝学研究所)
「ショウジョウバエ生殖細胞におけるエピトランスクリプトーム制御」 - S2-6 藤 泰子(東京工業大学)
「植物のエピゲノム修飾間クロストークがエピゲノムパターン形成を駆動する」 - S2-7 横林 しほり(京都大学 医学研究科)
「試験管内再構成系を用いたヒト始原生殖細胞発生とエピゲノム機序の理解」
【Symposium2】co-organized by Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas, Replication of non Geneome
Theme ”Regulation of Life Phenomena by Non-Genomic Information Mechanisms”
Organizer: Kei-ichiro Ishiguro (Kumamoto University IMEG)
- Outline and Aim of the Theme
- Sexual reproduction accompanies specific changes in chromosome, chromatin, and nuclear dynamics over a broad range of species. In this symposium, we will discuss chromosome/chromatin/nuclear dynamics from different aspects of sexual reproduction, such as germ cell differentiation, meiosis, sex determination, and fertilization.
- Program
- S2-1 Kei-ichiro Ishiguro (Kumamoto University IMEG)
Sexually different mechanism of meiosis initiation - S2-2 Azusa Inoue (RIKEN IMS)
Establishment mechanism of transgenerational histone modifications - S2-3 Makoto Tachibana (Osaka university)
Epigenetic Regulatory Mechanisms of Mouse Sex Determination - S2-4 Minoru Tanaka (Nagoya university)
Molecular Mechanism of Egg Formation Commitment - S2-5 Kuniaki Saito (National Institute of Genetics, Japan)
Epitranscriptome Regulation in Drosophila Germ Cells - S2-6 Taiko To (Tokyo Institute of Technology)
Crosstalk between plant epigenomic modifications drives epigenomic pattern formation - S2-7 Shihori Yokobayashi (Kyoto university)
Understanding human primordial germ cell development and epigenomic mechanisms using in vitro reconstituted systems
【シンポジウム3】
テーマ『お酒造りの酵母遺伝学:基礎、応用、未来』
2日目(9/7)15:30〜18:30 A会場(パレアホール)
世話人: 谷 時雄(熊本大学)
- テーマの概要とねらい
- 酵母は優れた代謝能力と分裂能力を持ち、古くから食品・醸造・製薬など、様々な産業に利用されてきた。特に酒類の醸造に用いられる酵母は、より香味の良い酒類を造り出す酵母を求めて、様々な育種改良が積み重ねられてきた。しかし、近年の酒類消費の減少や多様化、ゲノム編集技術などの開発に伴い、醸造用酵母の育種研究は新たな局面を迎えつつある。本シンポジウムでは、新規酵母育種技術の基礎研究から、今までお酒造りに使われたことのない分裂酵母の醸造応用まで、将来に向けた新しい醸造酵母遺伝学の展開について紹介する。
- プログラム
- 講演者:180分 言語:日本語
- S3-1 大矢禎一(東京大学新領域創成科学)
「ゲノム編集による清酒酵母の育種」 - S3-2 渡辺大輔(奈良先端大)
「清酒酵母は何を感知してアルコール発酵を調節しているのか?」 - S3-3 金井宗良(酒類総合研究所)
「清酒酵母らしさを特徴づける遺伝子の効率的同定方法の構築」 - S3-4 久冨泰資(福山大)
「ローカル酵母の分離解析から酒類の実地醸造まで」 - S3-5 谷時雄(放送大学/熊本大学)
「分裂酵母ジャポニカス吟醸香高生産株の育種と醸造応用」 - S3-6 高橋酵太郎(ダイヤモンドブルーイング)
「分裂酵母 Schizosaccharomyces japonicus Kumadai 株を用いたクラフトビールの醸造」 - S3-7 平田大(新潟大日本酒学センター)
「チェックポイント研究:清酒酵母への展開」
【Symposium 3】
Theme “Yeast Genetics in Sake Brewing: Basics, Applications, and Future”
Organizer: Tokio Tani (Kumamoto University/ The Open University of Japan)
- Outline and Aim of the Theme
- Yeast has excellent metabolic and growth abilities and has long been used in various industries, including food production, brewing, and pharmaceuticals. In particular, yeast used in the brewing of alcoholic beverages has undergone various breeding and improvement efforts in the development of yeast that can produce more flavorful alcoholic beverages. However, with the recent decline and diversification of liquor consumption and the development of new technologies such as genome editing, research on breeding yeasts for brewing is entering a new phase. In this symposium, we will introduce new developments for the future in the genetics of brewing yeasts, from basic research on new yeast breeding technologies to brewing applications of fission yeast that has never been used for sake production before.
- Program
- S3-1 Yoshikazu Ohya (University of Tokyo)
Genome editing of sake yeast strains - S3-2 Daisuke Watanabe (Nara Institute of Science and Technology)
What does sake yeast sense to control alcoholic fermentation? - S3-3 Muneyoshi Kanai (National Research Institute of Brewing)
Construction of an efficient identification method for genes that characterize ‘sake yeast identity’ - S3-4 Taisuke Hisatomi (Fukuyama University)
Isolation and characterization of local yeasts and their application in alcohol beverage production - S3-5 Tokio Tani (Kumamoto University/ The Open University of Japan)
Breeding and brewing application of fission yeast S. japonicus with high ginjo aroma production - S3-6 Koutaro Takahashi (Diamond Brewing Inc.)
Craft beer brewing with Kumadai strain of fission yeast - S3-7 Dai Hirata(Niigata University, Sakeology Center)
Research on checkpoints: Expansion to sake yeast
【シニアランチョンワークショップ】
テーマ『マイリサーチヒストリー:シニア会員レクチャー』
2日目(9/7)12:15〜13:15 A会場(パレアホール)
世話人:真木寿治(奈良先端大・バイオサイエンス領域・名誉教授)、平野博之(東京大・理学部・名誉教授)
- テーマの概要とねらい
- 昨年度末で大学を退職されるなどでシニア会員になられた会員に、ご自身の40年余の研究生活の歴史や所感を語ってもらい、遺伝学の進展・変遷の生き証人のストーリーを会員全体で共有する機会を持つことを目的にしています。特に、若い会員へのメッセージを伝える場となることを狙いにしていますので、学生および若手研究者の会員の皆様の参加を期待します。
- プログラム
- SW-1 石野 良純(九州大・農学部)
「大腸菌からアーキアへ:分子微生物学における40年の視点」 - SW-2 権藤 洋一(東海大・医学部)
「遺伝と遺伝子は違う:化学変異原から放射線まで」
【プレナリーワークショップ】
〜第94回大会BP賞受賞講演から〜
3日目(9/8)11:00〜12:00 A会場(パレアホール)
世話人:企画・集会幹事 沖 昌也(福井大学)
- 演者
- PW-1 岸野 廉(立教大学 理学部 生命理学科)
「IEE がトランスポゼースと共に誘起する特異な DNA 組換え反応」 - PW-2 梶谷 卓也(福井大学 学術研究院工学系部門 生物化学研究室)
「RNA polymerase Ⅱ Ser7リン酸化は、転写と共役したヌクレオソーム再構築を促進して転写一時停止を安定化する」 - PW-3 牛 小蛍(北海道大学生命科学大学院 生命科学専攻)
「シロイヌナズナにおける熱活性型レトロトランスポゾンの制御機構の解明」 - PW-4 赤瀬 太地(東京工業大学 生命理工学院、理化学研究所 生命医科学研究センター 生命医科学大容量データ技術研究チーム)
「ヒト非コード領域から翻訳される小さいタンパク質に対する機能性配列の探索」